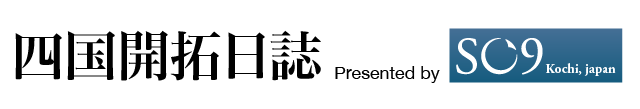轟九十九滝は、徳島県に3つある日本の滝百選のなかで、特に特徴的な景観を持っています。滝までの空間を遮る威圧的な両岸と、その奥でどうどうと流れ落ちる落差58mの水流。御神体として崇められるのも当然な、神の存在を感じる空間です。
日本の滝百選に選ばれる本滝の上流にも、見応えのある滝が連続し、滝好きにはたまらない経験ができるでしょう。
威圧的に狭い淵の奥に落ちる迫力の水流

滝見へと続く20mほどの廊下(淵)は、場所により幅およそ2mまで狭まり、最深部に落ちる本滝の轟音と飛沫を吐き出しています。決して日当たりの悪い方角ではないにもかかわらず、あまりにも狭められた水の廊下に日光が当たることはなく、常に凛とした空気を帯びています。
ただ、公称落差58mについては疑問が残り、目視できる範囲で30mほどでしょうか。有名な滝は落差詐称しているものが多く、例えば高知の御来光の滝(日本の滝百選)は公称102mに対し実際は64mの落差(ロープ長による実測)にとどまるなど、いささか大袈裟なことが多いようです。
しかしながら轟九十九滝・本滝の魅力は、その落差ではなく空間そのもので、決して魅力を損ねるものではありません。
轟九十九滝の滝たち
九十九滝というだけあり、本滝から上流にも複数の滝があり、遊歩道も整備されています。最上部とされる鍋割りの滝までは小一時間の道のりです。
二重の滝

本滝のすぐ上に位置する二重の滝。落差は6mほど、二条の水流を落とす滝です。
横見の滝

落ち口から吐き出された水流は宙を舞い、暗い淵へと吸い込まれていきます。落差は8mほどです。
船滝

細く圧縮された水流が岩の裂け目を落ちる舟滝。落差は約5m。
丸渕の滝

船滝のすぐ上部に位置し、滝壺を船滝の落ち口と共用する丸渕の滝。舟滝と丸渕の滝は2段の段瀑と捉えた方が自然な気がしますが、別々の名称がついています。落差は約10m。
鳥返しの滝

非常に大きな釜を持ちつ鳥返しの滝、惜しむべきは堆積物の多さでしょうか。それでも直径25mはあろうかという立派な滝壺は一見の価値あり。落差は約12m。
鍋割りの滝

本滝〜鳥返しの滝は結構連続していて気軽に散策できるのですが、鍋割りの滝だけは離れていて、鳥返しの滝から20分ほどかかります。落差は15mほど、近づけないのが少し残念です。
遊歩道の状況

滝巡りに利用する遊歩道は、階段にはじまり、一部ガレている部分もあるものの概ね歩きやすい状態です。ただ、滝が連続する渓谷沿いにつけられた遊歩道だけあって高低差が結構あります。最初の階段だけでも171段ありますので、くれぐれも歩きやすい格好で訪問するようにしてください。
滝壺に神輿が!勇壮な轟秋祭り

轟本滝の滝壺へ入っていく神輿
毎年11月第2日曜日に行われる轟秋祭りは、神輿が滝壺に入る滝渡御(たきとぎょ)をクライマックスとする勇壮な行事です。通常時から荘厳な景観が魅力的な轟本滝ですが、神輿が滝壺に向かっていく様からは、言葉では表現できないほどのエネルギーを感じることができます。