
四国三悪渓というものがある。足谷川・瓶壺谷(右俣)・松ヶ谷の3本をそう呼ぶらしいが、確かにそのどれもが一筋縄ではいかない悪さを持っている。
昨年、私に登攀的な沢登りを教えてくれた師匠とともに瓶壺谷を初訪問してから1年と少し。それから100本ほどの渓谷を遡行し、多少は登れるようになっている。当時は恐怖を感じながら師匠の背中を追うしかなかったが、今なら正面切って勝負できるかもしれない。
そして何より、瓶壺谷には完全遡行という甘美な果実がまだ残っているのだ。地元沢ヤ同人として我々がその果実をいただくしかない。瓶壺谷(右俣)完全遡行。
メンバー:ゴルジュクラブ3人|紀伊半島彷徨クラブ1人

連瀑帯の始まり
連日の雨で増水する瓶壺谷右俣に足を踏み入れる。ここから源頭部までの標高差600mは1つの連瀑帯になっている。
水量は多いが勝負できないほどではない。瓶壺谷右俣は集水域1.5km2の小渓谷である。

基本的にロープは出さない
昨年ロープを出して通過した滝もフリーでハイペースに進む。1年の経験が、私に当時とは全く違う景観を見せていた。

2段40m
2段40mに到着。通常ここから上部の35mをまとめて高巻きする。
完全遡行の大前提はこの核心部の水線突破。まずは下段の右水流を各々フリーで超える。

2段40m
中段には残置ビレイステーションがあった。
水流右を登り、CS下で左上に進路を変える。カムがよく決まる楽しいピッチ。

35m|1ピッチ目
今回のメインディッシュ。瓶壺谷で一番厳しい地形の中、垂直ゴルジュのように落下する35m。
1ピッチ目は右テラス状を中間部まで。A1。

35m|2ピッチ目
中間部の少し上になんと残置ハーケンを発見。場所から判断するに下降支点と思われる。
ここから先は恐らく我々が初めて登攀することになる。
凹角を3メートルほど上がり、水流に向かってバランシーなA1を2ポイント。水流横カンテから右上して凹角へ。100kgほどの泥やニラを掃除して掘り出したリスにハーケンをぶち込み落ち口へ。最後は思い切って落口CSに踏み込んだ。

ドヤ顔
35mを越えると谷は随分穏やかで開放的になる。とはいえ連瀑帯の真っ只中であることに変わりはない。

上部連瀑帯
どこまでも続く連瀑帯を進む。パーティーの足並みは揃っているためロープは必要ない。
どの滝も難しくはないが高度感抜群で落ちれば1発アウトだ。

ゴール
ゴール。
1年前、私に厳しい沢の面白さを教えてくれた瓶壺谷を、自分の手で完全遡行できてよかった。
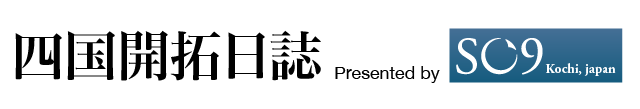

 執筆:ゴルジュクラブ
執筆:ゴルジュクラブ