
愛媛県・高知県・徳島県(香川県に沢登り向きの渓谷は存在しない)それぞれの定番コース概要と、未開の渓谷がゴロゴロしている四国の沢登り開拓について記述します。
関西起点沢登りコース100・日本登山大系等に記載の沢は概ね登っていますが、それだけでは不十分なので地元沢ヤお勧めの渓谷など、厳選した沢だけ掲載しています。ざっくりとした掲載基準は遠征してまで行く価値があるか否か、という感じです。
『(四国の)沢登りに関してはネットでの情報が極端に少ない為、書籍頼みになる』(某著名沢ヤ ブログより)。
情報がなくて四国の沢のことがよくわからないそこの君。これが四国で行くべき渓谷リストだ。
執筆:ゴルジュ開拓同人『ゴルジュクラブ』
四国の定番沢登りコース
難易度は主観です。
初級:テキトーでOK
中級:ロープワークとある程度の経験が必要
上級:一般的ではない
愛媛県の沢登りコース
面河渓本流
初級|日帰り(巻き主体)
上級|1泊2日(直登)
*巻きは概ね簡単

下部に大水量ゴルジュ、中部に牧歌的な花崗岩ナメ、上部に日本百名瀑「御来光の滝」を擁し、源頭部は選ぶコースによって日本百名山の石鎚山に突き上げる、四国を代表する渓谷。入渓直後の水量は四国最大級で、本流遡行ならではの醍醐味を味わえる。花崗岩を主体とした明るい渓相が特徴。

四国では珍しい大水量ゴルジュ
一番の難所となる下部ゴルジュは並走する遊歩道で容易に回避でき、御来光の滝も右岸から容易に巻ける。下部ゴルジュはエイドクライミングを要する登攀・御来光の滝は左壁から登攀可能でもあるので力量に応じたコース取りをできる。御来光の滝上部には高巻きすると見ることのできない斜瀑15mが隠されている。
巻き主体の一般的な行程では日帰りが可能なものの、コースタイムは長い。詰め上がる沢筋の選択によっては若干緊張する場面もある。石鎚スカイライン上部「土小屋」に車をデポすれば下山をショートカットできる。また、御来光の滝高巻き道途中から下山道にエスケープする踏み跡がある。石鎚山山頂から入渓点まで歩いて下山する場合は3時間。下部ゴルジュ・御来光の滝の登攀をする場合は1泊2日必要。泊適地は各所にある。
2023.08.29 面河渓|沢登り|下部ゴルジュ〜御来光の滝登攀
坂瀬川
中級|日帰り

文句のつけようがない名渓。四国の名渓オブザベスト。入渓地点からすぐに四国らしい変性岩泳ぎゴルジュがはじまり、中部で花崗岩のスッキリとした渓相になる。岩質が変わってすぐに見栄えの良い滝が数本連続し、滑床の癒し渓となる。勾配のない渓谷でロープが必要な箇所は少ないが水線突破する場合はそれなりのタクティクスが必要。

ほぼ全ての滝が直登可能で、巻きは容易かつ下山も並走する林道で2時間と沢登りのためにあるかのような渓谷。下部ゴルジュは四国では珍しい泳ぎ系ゴルジュで、水量次第で大きく難易度が変化する。いずれにしても巻きが難しい渓谷ではない。

周辺の植生は石鎚山らしく落葉樹の美しい樹林が続き、同じ滑床といえ紀伊半島や九州のそれとは一線を画す。
鉄砲石川
初級|日帰り

四国の癒し渓代表。さしたる難所はなく、釜やナメが連続する。非常に日当たりが良い沢で、開放的な空間が終始続くため是非とも晴天時に訪れたい。上部に若干緊張を強いられる滝が数本現れるがどれも10m未満かつ岩がしっかりしているので落ち着いて挑めば問題は無い。
四国の沢で沢登り初心者をエスコートするなら鉄砲石川がベスト。初っ端からため息が出るほどに美しい大釜を携えた滝を抜け、50mを越す迫力の岸壁や天まで伸びる支流のスラブ滝を拝みながら、ただただ美しい花崗岩の沢ハイキングとなる。二俣を左にとると大型車が行き違えるほどの滑床がしばらく続く。原頭部でいくつかの滝を越えると、最後は四国山脈ならではの笹原に詰め上がる文句のつけようがない名コース。
源頭まで上り詰めると石鎚山を望む絶好の縦走路に飛び出す。下山は3時間。
千本滝沢
初級|日帰り

鉄砲石川の支流。その名の通り、最初から最後まで標高差600m以上の連瀑帯が続く。ロープが必要かどうかはパーティーの力量次第で、熟達者であれば全ての滝を快適にシャワークライムできる。源頭から稜線の藪漕ぎがウザい。稜線に出てもそれほど明瞭な踏み跡があるわけではなく、下降路のセンスが問われる。
瓶壺谷(右俣)
上級|日帰り

瓶壺谷(右俣)|沢登り|完全遡行
遡行記録がある渓谷のなかでは四国最難関とされる。瓶壺谷右俣に足を踏み入れてからの標高差600mは全てコンティニュアスな連瀑帯。地形図からは想像できないほど脱出が難しい地形をしていて、滝の直登もしくは渋い高巻きの連続となる。大連瀑帯を抜けるとすぐに名峰「瓶ヶ森」の笹原を流れる滑床に飛び出し、そのまま登山道へと合流する。瓶ヶ森登山口に車をデポできるなら下山は0.5時間。歩いて下山する場合は3時間。
集水域の小さい渓谷ゆえ渇水時は面白みに欠ける景観となるが、難易度に変わりはない。
西種子川
中級|日帰り
不明(魔戸ゴルジュ)

入渓直後に魔戸の滝(40m)から続く総落差150mの魔戸ゴルジュを擁す。魔戸ゴルジュは断片的な記録こそあるものの、全体を通して下部から登攀した記録はなく、キャニオニングでしか進入不可のセクションもある。
全般的によくまとまった渓谷だが、魔戸ゴルジュを除けばそれほど特筆すべき点はない。魔戸ゴルジュ中間(屈曲部)から入渓すると直後にロープを要する高巻きが2回連続する。1回目の高巻きは気持ち悪い苔の斜面をトラバースすることになり緊張する。より一般的な魔戸ゴルジュ上部からの入渓であれば最後までロープは使用しない。全体的に巻き主体の沢登りとなるため、遡行図を事前に確認しておけば難しい部分はない。
赤石山系の北斜面に位置する渓谷で、真夏でないと薄暗い。
赤石山系北面の渓谷は水の色が独特だ。写真に表現できなくて恐縮ではあるが、青く寒々しい水の色をしている。日本100名渓に選ばれているのも納得の渓相、ではあるが高巻き主体になるのが玉に瑕。下山は並走する登山道で2.5時間。
瀬場谷
中級|日帰り

大滝「八間滝」
大滝を含め全ての滝が容易に直登できる、沢登りのためにあるかのような渓谷(某有名ガイド本の紹介文)。四国の沢登りコースで1.2を争う人気で中級の沢入門編。登りやすい滝が多くシャワークライムを存分に満喫できる一方でゴルジュ地形がないのは残念。ゴーロ帯が無く間延のない名渓であることは確か。
大滝「八間滝」も技術的には難しくなく登攀可能だが一般的には高巻きとなる。
滝を直登できるという点において人気を集めるのは納得だが、ゴルジュ地形がないのがは残念。あくまでもシャワークライミングを楽しむための渓谷である。下山は並走する登山道で2時間。
肉淵谷
中級|日帰り

下部に直登可能で見栄えの良い大滝が連続する。小渓谷ではあるが滝の登攀を楽しむにはうってつけの渓谷。滝の登攀にはロープ必須のため初級者だけでの挑戦は控えたい。いずれの滝も高巻きは容易。

上部には小ゴルジュが断続し力量に応じてコースどりできる地形も相まって楽しませてくれる。下山は1本東の小渓谷を下ると滑床・大滝など結構楽しめる。2.5時間。
中流部の側壁に大瀑布「肉瀑(2023.08.25|初登)」がある。
伊予富士谷
中級|1泊2日

四国では珍しい泊まり沢。さしたる難所はないが急峻な地形での高巻きはルートファインディングミスで大きく時間ロスする可能性があり、中級者向け。有名な二股のスケール感は噂通りの四国離れしたもの。
源頭まで上り詰めると人気のハイキングコース「伊予富士」支尾根にあるカッコいい岩峰に飛び出る。2つの岩峰を越えながらシャクナゲの藪漕ぎ小1時間でよく整備された登山道に出る。伊予富士最寄りの登山口(瓶ヶ森林道上)に車をデポすれば下山は1.5時間。車をデポしない場合は舗装林道歩き3時間が追加となる。
全体を通して特筆すべき難所はないものの、ロープが必要なクライミングが数カ所あり、ルートファインディングで大きく難易度が変わる高巻き・詰めの急登など沢登りの総合力が試される。
床鍋川
初級|日帰り

源頭は開放的な空間
多くの滝が直登可能で、上部は開放的な空間での沢登りとなる。初心者を案内するのによく使われる渓谷。
大滝登攀が容易で、そこから続く上部ナメ地帯も快適に遡行可能、下山も簡単なのが親しまれる理由か。初級と中級の中間くらいに位置する渓谷で、ロープなしでは心許ないが必須ではない。
世界で2箇所しか産出されない貴重な「エクロジャイト」が源頭部に散見される。下山は並走する登山道で2時間。
足谷川
上級|日帰り

四国を代表する悪渓。終始ゴルジュ地形の泳ぎ渓で、上部に沢登りでの侵入を今だに許していない連瀑帯をもつ(2023年上部ゴルジュ完全遡行|2023.10.11 足谷川(愛媛県)|沢登り|下部〜上部ゴルジュ ワンプッシュ)。一般的には四国最難関とされている。
経験を積んだ沢ヤにしか突破を許さない厳しいゴルジュが終始連続する。記録が少ない四国の沢らしく、明確なルートの記録がないのも上級者にとっては楽しめるポイントとなるだろう。顕著なゴルジュが連続する沢は四国では珍しく、それだけでも遡行価値が高い。
沢登りの対象となるのは国道沿いの入渓点から別子銅山の産業遺跡地帯「東平(とうなる)」までの区間で、それより上は特筆すべき点のない渓相となる。東平からの下山は登山道で1.5時間。入渓点から10分の場所に温泉併設の道の駅がある。
高瀑渓谷
中級|1泊2日
不明(下部ゴルジュ・高瀑)

高瀑渓谷|沢登り|下部 – 上部ゴルジュ完全遡行
50cmゴルジュにはじまる突破困難なゴルジュ帯をもち、源頭部には落差132mの西日本第二の大瀑布「高瀑」を擁す渓谷。下部ゴルジュより下流はゴーロが多く退屈。林道でco820m付近まで標高を上げ支流沿いに入渓すると楽しいセクションだけ遡行できる。

50cmゴルジュ
中部の50cmゴルジュから続く下部ゴルジュ帯は限られたものにしか通過を許さない厳しさをもつ。遡行記録の少ない渓谷かつゴルジュ・滝が多いため高巻き主体の場合は面白みにかける。水線突破できる力量があれば滝・ゴルジュ共に1級品で、四国を代表する名渓である。
高瀑で遡行を打ち切るのが一般的で、下山は登山道1.5時間+林道4時間。
2023.08.27 高瀑渓谷|沢登り|下部 – 上部ゴルジュ完全遡行
滑床渓谷
初級|日帰り

延べ数キロにわたる花崗岩の滑床をもつ渓谷。日本の滝百選に選ばれる大スラブ滝「雪輪の滝」を擁す。厳しい地形はなく、登山道が並走するため沢靴さえあればハイキング感覚で沢歩きを満喫できる。滑床ばかりが注目されがちだが、源頭となる鬼ヶ城山系は四国きってのブナの巨木林を擁す山域で、新緑や紅葉の時期は沢登りからの縦走ハイキングが最高。下部セクションではキャニオンニングツアーも盛んに行われている。
四国最果て(四国最果てということは日本最果てとも言える)エリアに位置していて、四国の他の渓谷とは明らかに異なる特徴を持っている。全くの初心者でも沢靴さえあれば楽しめる貴重な1本。
下山は千畳敷から登山道で1時間。縦走コースからはコースどりによるが2.5〜4時間。
高知県の沢登りコース
高知県はアクセスが悪すぎるためインターネット上に遡行記録はほとんど無い。
インターネット・SNS・書籍に記録のない渓谷の情報はこちら「GORGE CLUB (四国の渓谷開拓記録集 2024)」。
安居渓谷(弘沢)
初級|日帰り
上級|日帰り(直登)

仁淀ブルーで有名な安居渓谷の支流。さしたる難所はなく、全ての巻きが5分で終了するコンビニ系癒し渓と侮るなかれ、全ての滝が直登可能で登攀系の沢としても見逃せない1本。
コンティニュアスではないが間延びすることもなく、バリエーション豊かな滝が次々と現れて楽しませてくれる。なかでも中部のゴルジュ地形の斜瀑(容易に直登可能)から続くプチゴルジュや白眉「屏風滝」など単体でも特異性を持つ地形を擁す。
高知県で一般的な沢登りコースは安居渓谷1本しか無いことになっている。他にも沢山良い沢があるが、その中でも確かによくできた渓谷で、初心者から上級者まで楽しませてくれる懐の深さがある。
脱渓点に車をデポできればツアーさながらのリーズナブルさで下山可能。そうでない場合は2.5時間の林道歩きとなる。
徳島県の沢登りコース
徳島県はアクセスが悪すぎるためインターネット上に遡行記録はほとんど無い。
インターネット・SNS・書籍に記録のない渓谷の情報はこちら「GORGE CLUB (四国の渓谷開拓記録集 2024)」。
祖谷渓
初級|日帰り

沢登りの対象としては大味すぎる感じがしないでもない大渓谷で、ほぼ泳ぎのみの牧歌的な空間をもつ。沢登りの対象として興味深い支流を何本かもつ。
日本最後の秘境、と大々的に売り出している秘境の皮を被った観光地中心にありながら、本当の秘境さながらの空間が残っている。泳ぐことさえできれば沢登りの知識がなくても結構楽しめてしまうリーズナブルさも魅力か。
「祖谷渓キャンプ村」から下流に向かって入渓するのが一般的。帰りは一部水流に逆らっての泳ぎを交えながら入渓点に戻る。
トチグルス谷
初級|日帰り

遡行記録のない渓谷だが、入渓直後から始まるゴルジュ地形、その後も断続的に現れるゴルジュ滝は沢登りの対象として非常に魅力が高い。
そのほとんどが直登可能で、登攀系の沢としての資質がある。一方ですべての滝を小巻きできるリーズナブルさも併せ持つ。
小渓谷ゆえ平水時は面白みに欠ける。
2023.08.13 トチグルス谷(徳島県|神山町)|沢登り
かずろう谷川
初級|日帰り

いくつかの特徴的な大滝と小ゴルジュを内包する渓谷。高巻きが容易な地形をしていてアプローチ・下山も容易なため初心者のエスコートにも最適と思われる。
記録が少ない四国の沢登りコース
山岳ばかりというか山岳しかない四国では当然沢の数も多い。地形は急峻、降水量も多く紀伊半島のように沢登りの聖地となっていてもおかしくない条件が揃っていますが、愛媛県の、それも石鎚・赤石山系を除けば、四国における沢登りの情報は皆無です。
四国の沢登り開拓
徳島県の剣山周辺にはロクな沢が無い(某有名登山情報誌)だとか、高知はゴーロだらけのクソ沢ばかり(スーパースター)、など言われたい放題の四国エリアですが、執着を持って探せば素晴らしい渓谷がまだまだたくさん眠っています。記録未見で初遡行の喜びを感じられる渓谷も多く、沢登りにおいて四国は日本最後のフロンティアと表現しても過言ではないでしょう。
四国での(開拓的な)沢登りは、淵を泳ぎ、滝を直登して水線を遡行すれば、記録未見の滝やゴルジュが次々に現れ、初遡行の喜びを存分に味わうことができます。過去、山岳会の活動が活発だった頃に部分的に遡行されている渓谷はあるものの、水線突破による全貌解明がなされている渓谷は少なく、現代の装備や技術を持って挑戦すれば意外なほど多くの発見があるはず。
ここに、記録未見(各種ガイド本・WEB・SNSに情報がない)の沢を少し紹介します。詳細は「GORGE CLUB (四国の渓谷開拓記録集 2024)」に掲載。
記録未見の沢は、行動中常にロープを出すような登攀系をはじめ、泳ぎからのボルダー系、大水量ゴルジュ、大滝登攀など多種多様です。ロープを要する高巻きや水流に逆らっての登攀、キャニオニング以外で侵入不可など結構シビアなものが多く、中・上級者向きが揃っています。
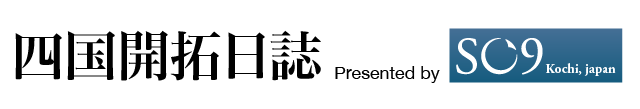

















 執筆:ゴルジュクラブ
執筆:ゴルジュクラブ
コメント