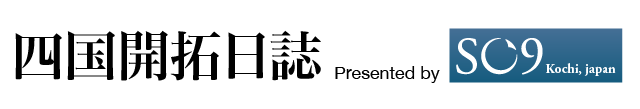夫婦二人で高知に移住して、2年と3ヶ月が経過しました。
半年以上ブログを放置していた理由は、嬉しいことに仕事が忙しかったことと、リノベーションが進んでいなくてネタがなかったためです。
実は、以前の記事「高知移住5ヶ月。古民家リノベーションが進んできました。」で結構順調にリノベーションが進んでいると書きましたが、その後、古民家特有の問題にいろいろ直面して途方に暮れていたこともあり、最近までちっともリノベーションが進んでいませんでした。
湿気・気密性・水まわり
古民家に住み始める前からわかっていました。「湿気・気密性・水まわり」について、いずれは対策が必要だと。
住み始めて一年間は、人生で初めての古民家生活ということもあり、辛かったり不快な問題が生じても、イベント気分で乗り越えることができました。普通の感覚からすれば不快な体験でも、非日常的なテンションによって耐えられるのです。「こんな所にもカビが生えてる!」「風呂場寒すぎでしょ!」とか楽しむ余裕すらあります。
ところが2シーズン目になると、これから生じる辛いイベントが事前にわかっているので、楽しむような気分ではなく、ただただウンザリするように心境が変化してしまいました。すぐにカビの生える食器も、年中外気温と変わらない室温も、ずっと続くという実感がわいたことで耐えられなくなったのです。
実際どんな状況だったのか
具体的にどんな状態だったのかを羅列するとこんな感じです。
- 梅雨は土間のコンクリートから水が染み出して室内に水溜りができる
- 気密性が低く冷房・暖房・除湿がほぼ不可能
- 冬場は風呂場・トイレが氷点下
などなど、想像よりもかなり厳しく2年目には「勘弁してくれ・・・」という感覚しかありませんでした。
リノベーション
「ここに一生暮らすのであれば、どう考えても今のままじゃダメだ。」
古民家の住環境が当たり前の時代に育ったのであれば、耐えられるのかもしれない。しかし、平成の時代に生まれて快適な住環境で暮らしてきた私たち(両親には感謝するばかり)にとって、昔ながらの住環境は苦痛に感じる部分が多すぎます。
これまでは、「粗大ゴミを捨てた」「床にフローリングを張った」など、表層リノベーションがほとんどでした。これらは小さな労力で見た目の変化が大きく、ブログやSNSで承認欲求を満たすにはとても良いものでした。ただ、見た目こそ綺麗になれど住宅の性能はほとんど向上しないため、結局入居当時の環境で無理やり暮らしているにすぎません。
四季を通し暮らしてみて嫌というほど実感したのは、根本的なリノベーションをしない限り快適な生活は実現しないということ。ただ気づいたからと言って簡単にできるものではなく、まずはどの程度手を入れるのかしっかりと考察する必要がありました。
新築か、リノベーションか
我が家は住宅購入費用+リノベーション費用として支出できるのは1000万円と決めていましたので、ほとんどの作業をDIYしなけらばならないことは確実でした。
実は、同じ性能の住宅を作るのならば、新築の方が技術的難易度が低く、既存家屋の解体コストを考えれば古民家リノベーションと新築に費用面での差はほとんどありません。
技術面においても新築ならば「プレカット」と呼ばれる機械加工済みの木材を使用できますし、現代の建材サイズにあわせた設計をすればその後の工程も楽になります。一方で古民家を本格的にリノベーションするとなると、全てが現場合わせ、それこそ職人的な技能が求められるシーンが多く、また、更地での新築と違い、不要部分の解体から作業を始める必要があるなど、技術的に難しく、費用的にもそれほどメリットがありません。
古民家での「現場合わせ・解体・廃棄」のコストの方が、新築の「材料費」よりも高くつく場合が多いのです。
それでも私たちがリノベーションにこだわったのには、いくつかの理由があります。
1.市街化調整区域
これは物件購入時に初めて知ったのですが、土地種目の中には「市街化調整区域」というものがあり、ざっくりいうと「既存と同じ目的、同じ規模の建築物しか建てることができない」というものです。私たちの自宅が建っている土地も市街化調整区域のため、新築を建てるためには、土地の測量のやり直しや複雑極まりない申請の必要があるなど、建築以前に結構なコストが発生することが判明しました。
結構便利な立地なのに周辺に住宅がない、そこが気に入っていたポイントでしたが、住宅がない理由は市街化調整区域だからでした。しかし、現状の躯体を利用してリノベーションするのであれば申請は不要、しかも未来永劫まわりに住宅が立つ可能性が無い、となればメリットと捉えることも可能です。
2.地域の財産保護
現代において、古民家と同じ工法で建築するとなると莫大なコストがかかります。せっかく(ギリギリの状態で)再利用できそうな状態を保っている古民家なのですから、難しいから、という理由で壊してしまうのはもったいない。我が家は地域で一番目立つ立地で、余所者である私たちの一存で綺麗さっぱり変えてしまうのもどうか、という点も気になりました。
また、古民家ならではの「小屋組み」と呼ばれる屋根周辺の構造は、それは美しいもので、うまくリノベーションすれば自慢できそう、という下心もありました。
覚悟のスケルトンリノベーション
この古民家に一生暮らすからには徹底的にやろう。
快適性を向上させるには、第一に地面からの湿気を遮断する必要があります。昔ながらの、土むき出しの床下から際限なく放出される湿気をなんとかしないと、湿気対策の第一歩を踏み出すことすらできません。
湿気対策の方法は2通りあって、1つ目はビニールシート+砂で対策するもの。これは安価なうえに効果があり(これまでの1年半で部分的に試したら結構効果があった)一般的なリノベーションで採用されることが多い方法です。2つ目は家を持ち上げるなどして現代基準の基礎を作るもの。こちらは技術的・コスト的に1つ目とは比較にならないほど大変ですが、湿気対策だけでなく耐震化にもメリットがある方法です。
我が家は床下の湿度が高かったためか20年間の空き家期間のためか腐食している部分が多く、湿気対策のみでなくそれらの補強や修繕も必須でした。また、傷んでいる部材が多いことから耐震化も部分的に大きな力が発生する(耐震化リノベーションに多い)方法ではなく全体的な計画が必須と判断、その前提となる基礎を作ることに決定しました。
続き
基礎打設完了、しかし
基礎の打設が終わり、やっと一安心と思いきや、柱周辺の今後不要となる部材を撤去してみると、想像以上に腐食が激しい部分を複数発見したりと、まだまだ安心できそうにありません。
ただ、ひとまずは安定した基礎を作ることができたので、次は屋根を仕上げて、それから柱や壁に取り掛かろうと思います。